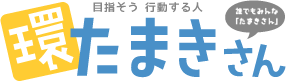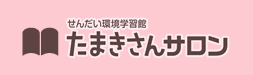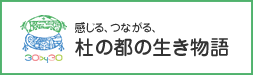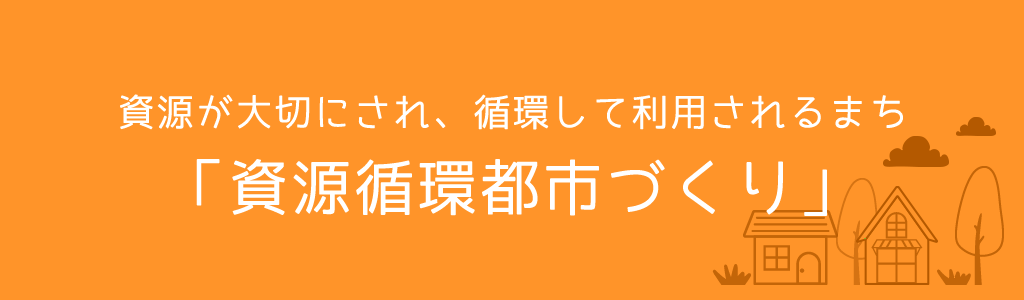�u�z�����m�ɂȂ낤�I�|�n�������ݏo���s�v�c�Ȑ��E�|�v���J�Â��܂��� 
���e���F2025�N04��02���i���j
���܂�����T�����X�^�b�t�ł��B
3��15��(�y)�ɓ��k��w��w�@���Ȋw�����ȁu���������i�Z���^�[�v�̑��늰 ���C�y�������u�t�ɂ��}�����āA�u�z�����m�ɂȂ낤!-�n�������ݏo���s�v�c�Ȑ��E-�v�Ƒ肵���T�����u�����J�Â��܂����B
�W�{�쐬��ώ@�E������ʂ��āA�z���̕s�v�c��ʔ����ɂ��ċ����Ă��������܂����B

�y�z���Ƃ�?�z
�Ђƌ��Œ�`����Ȃ�u�n���̍�p�ɂ���č��ꂽ�A�قڈ��̉��w�g���ƌ��q�z������V�R�̕����v�ƂȂ�܂����A���̒��ł͂��܂��C���[�W�o���܂���B
�搶���ǂ���������Ă���܂����B
���������悭����u�H��(������)�v���l���Ă݂܂��傤�B��ɊC������l�H�I�ɉ��H�������ꂽ�����i�g���E���̌����ł����A��`�ɏ]���A����͍z���Ƃ͌����܂���B
���l�ɉ����i�g���E���̉������Ɂu�≖�v������܂��B����͓V�R�ɎY�o���A���Â̊C���̌������ɂ���Ăł����z���ƌ����܂��B
�����ɔF�肳��Ă��邾���ł�6,000��ȏ�A���{�ł͂���܂ł�1,300��ȏ�̍z���̎Y�o���m�F����Ă��܂��B
����ȍz���̓�������͎��̂Ƃ���ł��B
�E�`:��A�����A����A�j��ȂǁB�E�F:�z���{���̗l�X�ȐF�̂ق��A���ʐ����Ȃǂɂ��e���Ŗ{�������Ă��Ȃ��F������܂��B
�E����:��������A�K���X����A��������A�^�����ȂǁB�E�ւ��J:����������ʂɂȂ邱�ƁB
�E�d��:���[�X�d�x�ŕ\���B���x10=�_�C�������h
�E���̑�:����A�����A�����A����(�u��)�A���˔\�ȂǁB
����̍u���ł́A���̓��u����(�u��)�v�Ɓu���˔\�v�̐��������z�����g���Ď������s���܂����B
�y����➀�@�u���z���z

���ۂɎ��O���ĂČu���̗l�q���ώ@���Ă݂܂���
����́A�T���v���z���Ƃ��āu�]�����z(�č��t�����N�����z�R�Y)�v���g���܂����B
�������ɔ�ׂĔg�����Z�������G�l���M�[�����������O���Ă�ƁA�z���̒��̌��q��C�I�������G�l���M�[���z�����āA���̒��̓d�q����C�ɃG�l���M�[��������N(�ꂢ��)��ԂƂȂ�A��蒷���g���̃G�l���M�[����o���Ȃ��猳�̏�Ԃɖ߂鎞�Ɍ����Č����܂��B
*����̕W�{���Ŏg���u�D�H�ў�(�������낢��)�v�ɂ��A�u�D�d��(�������イ����)�v�Ƃ����z�����t���Ă���ꍇ������,�Z�g�����O���Ă�Ɛ�������܂��B
�y�z���W�{�쐬�z
�z�������W���ώ@���������ōł��d�v�Ȋ�{�I�ȍ�ƂƂȂ�u�W�{�쐬�v�̍H�����A���ۂɍs���Ă݂܂����B

���l�̂���W�{�ɂ��邽�߂ɂ́A���⌋���̏�Ԃ��d�v�ł����A�̎悳�ꂽ�u�Y�n�v�̋L�ڂ��Ȃ���Ă���W�{�ł���Ƃ������Ƃ���ԑ厖�Ȃ��Ƃł��B

�Q���ґS���ŁA�u�Ήp(�����A�{�茧�Ô[�z�R�Y)�v�Ɓu���S�z(�Q�n������Ȓ��䓰��Y)�v�A�����āu���`�A�_��(�u���W���A�~�i�X�E�W�F���C�X�B�Y)�v�Ɓu�D�H�ў�(�������낢���A�������ɒB�i��z�R�Y)�v�̕W�{�Â���ɒ���!

�����Ń��x���܂ō쐬����ƁA�B�ꖳ��̕W�{���o���オ�������o�������킫������܂��B

�z���W�{�p�̃��x���Ɂu�z�����v�u�Y�n�v�u�̏W�����v�u�̏W�ҁv�Ȃǂ��������݁A�z���ƈꏏ�Ɏ����Ɋi�[���܂��B
�y�����A�@���ː��z���z
���ː��Ƃ́A���G�l���M�[�̓d���g�⍂���̗��q���̂������̂ł��B���ː�����o������ː������́A����������芪������(�F���A��n�A��A��C�A�H�ו��Ȃ�)�ɏ펞���݂��Ă��܂��B
�����̎��R���ː��ʂ͏Z��ł���ꏊ�ɂ���Ă��ς��܂����A���ς���ƔN�Ԃ�2.0�`2.5mSv(�~���V�[�x���g)�ʂɂȂ�܂��B
����X��������1����0.06mSv�ACT�����ł�1���2.4�`12.9mSv�̔�����ʂɂȂ�ƌ����Ă��܂��B

�����ɁA�V���`���[�V�����T�[�x�C���[�^(���ː������̂��ƁB�ȉ��T�[�x�C���[�^)���g���āA���܂�����T���������ł̕��ː��ʂ��v���Ă݂܂��B
0.02�`0.03μSv/h(�}�C�N���V�[�x���g)�Ƃ������l�ł����B
1�N�ԂɊ��Z����ƁA0.17�`0.26mSv(�~���V�[�x���g)�ʂɂȂ�܂��B������u�o�b�N�O���E���h���ː��v�ƌĂсA���̏ꏊ���ƂɈ�����l�������܂��B
�y�������/�Ւf�����z
��̒��ɂ����˔\���������z��������܂��B�E������W�E���Ȃǂ̕��ː����f���܂�ł��܂��B
����g�������ː��z���́A���ׂĕ������Y�́u�C�b�g���A�v�u�ΐ�v�u���[�N�Z���v�u�T�}���X�L�[�v��4��ނŁA�l�̂ɂقƂ�lje�����y�ڂ��Ȃ����x�̕��ː��ʂ̂��̂ł��B

�T�[�x�C���[�^�������ɋ߂Â��Ă����A���ʂ𑪒肵�܂��B

10cm�A5cm�A3cm�Ƃ����Ԋu�ōz��(���ː���)�ɋ߂Â��Ă����܂����B���ɁA�v�����ꂽ���l�����قǑ������o�b�N�O���E���h���ː��ʂ��������l�����߂܂��B
����̎������ʂ��O���t�����Ă݂�ƁA���ː��z������̉e��(���ː���)�ɂ��āA���̂悤�Ȃ��Ƃ��킩��܂����B
➀�����@���ː������狗���������A�e�������Ȃ��B
�A�����@���ː����Ɛڂ��鎞�Ԃ�Z������A�e�������Ȃ��B
�B�Օ��@���ː����Ƃ̎Օ����̌����A�Օ����̑f�ނɂ���ĕς��B�A���~�j�E���ł͂قƂ�Ǖ��ː����Ղ邱�Ƃ͂ł��܂���ł������A���͎Օ����ʂ��傫���Ƃ������Ƃ��킩��܂����B
�y�܂Ƃ߁z
�z���́A�P���ɔ����������ł͂Ȃ������̂��Ƃ�����Ă���܂��B�z���������������m�邱�Ƃɂ���āA�Y�o�n�悾���ł͂Ȃ��n���A�F���̗��j�܂łЂ��������Ƃ��ł���\�����߂Ă��܂��B
�V�����̍z�����A���N100��ވʌ�����Ƃ������Ƃł��B
�܂��ŋ߂́A�u�]�D��(������������)�v�Ƃ����z�����g���āA�������ʃK�X�̈�ł����_���Y�f���Œ肷��Ƃ����Z�p�̌����J�����A���k��w�Ői�߂��Ă��邻���ł��B

�����N���������Đ��݂����ꂽ�z���������Ă���d���Ȕ������▣�͓I�ȋP���A�����ėl�X�ȕs�v�c�Ȑ����ɂ��āA������̌���ʂ��ċ����Ă��������܂����B
�u�t�̑��搶�A�u���ɂ��Q�������������F����A���肪�Ƃ��������܂����B
�y�Q�l�����z
�E���� ��(2022)�u�}�� �z������Ӓ莖�T[��2��]�v������ЏG�a�V�X�e��.
�E���k��w���R�Ȋw���������e�L�X�g�ҏW�ψ��� ��(2009)�u���R�Ȋw���������v���k��w�o�ʼn�
���������������������@
���܂�����T���� �T�����u��
���܂�����T����
*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*
�������w�K�ف@���܂�����T����
���@���@ 10:00�`20:30
�y���j�@ 10:00�`17:00
�x�ٓ��@ ���j(���j���x���̏ꍇ�́A���̗���)�x���̗����E�N���N�n
*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*�d*